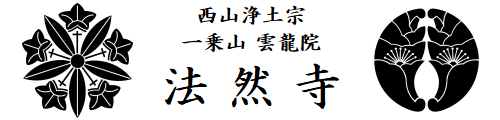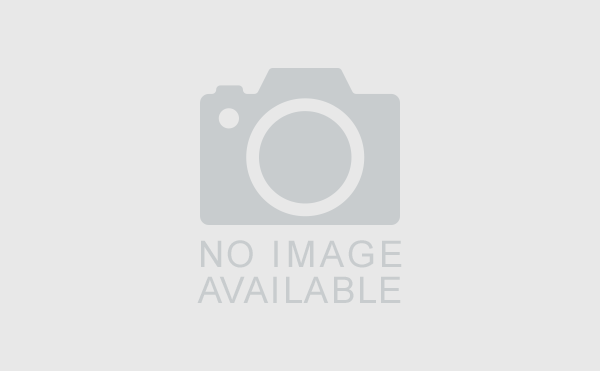西山声明の楽理「① はじめに」
はじめに
西山(せいざん)声明(しょうみょう)の楽理(がくり)というと何のことやらと思いますが、簡単に言うと「お経の音楽理論」です。
西山(せいざん)は「西山浄土宗(せいざんじょうどしゅう)の」という意味で、声明(しょうみょう)とは「お経」の事、楽理とは「音楽理論」の略となります。
「お経に音楽理論などあるのか。」そう思う方も多いと思います。お経とは、お釈迦様のお言葉であり、真理を表すものです。お経が唱えられる時には唱える人の信仰が現れるもので、僧侶にとっては真理の世界を表現するものです。それは理論などというものでは括れない世界である事は疑いようのない事実であります。
実際、私達僧侶の中では、お経は古来より「耳で唱える」という事が伝えられてきました。
それはお経の音楽性というのは師匠から弟子へ伝えられていくものであり、また地域によって、その人の個性や感性によって、微妙に変わってくるものでもあるからです。
しかし、本山(ほんざん)に色々な地方から僧侶が集まりお経を唱えるとそれぞれの地域のお経が調和し、一体となったお経が演奏されます。これは、お経は自由に演奏されながらも、芯となる音楽理論があり、それは伝承の中で存在しているからです。
その音楽理論とはどのようなものであるのか。現在の西山声明の楽理について自宗・他宗、その他の資料を参考にまとめさせていただきます。
なお、大事な事なのでもう一度お話させていただきますが、お経は自由に唱えられるものであり、理論に従って唱えられるべきではありません。一般の方は音階など考えずに自由に詠んで頂くのがいいと思います。
また、多くの僧侶は、これらの音楽理論を理解しているわけでは無く、耳で聴き、体全体で覚えて演奏をしております。
声明の音楽としての奥深さを知って頂く為の一つの分析として読んで頂けると幸いです。
声明とは
声明(しょうみょう)とはサンスクリット語で、「シャブタ・ビドヤ」という言葉の漢訳音写語で、シャブタは音声・言語を意味し、ビドヤは学んで明らかにする事を意味します。すなわち、物事を明らかにするという意味で、古代インドにおける学問区分、五明の一つとなっています。
中国で、音声・言語を意味するシャブタには「声」、学んで明らかにするビドヤには「明」の文字が当てられ、「声明」と表す様になりました。
その声明という学問が、中国で仏教の儀式音楽という意味で使われるようになり、仏教の伝来と共に日本に入ってきました。
声明というと、さまざまな旋律に乗せて唱えるもの、という印象があるかもしれませんが、旋律がなく経典を唱える読経も声明として差支えありません。
声明の楽理シリーズ目次(予定)
①はじめに
②声明の音階
②-1 声明の音階
②-2 音名 十二律について
②-3 階名 五音について
③声明の調子
④声明の博士(音符)
⑤声明の拍子