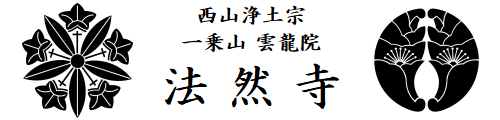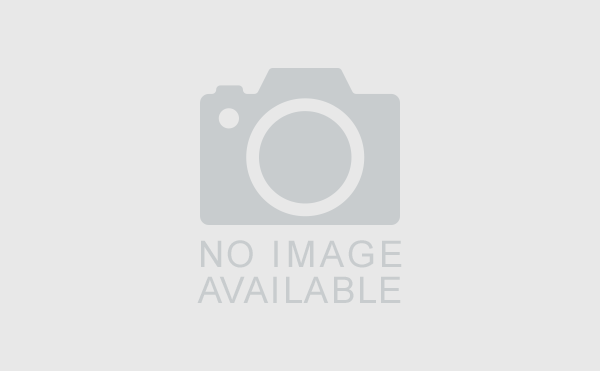西山声明の楽理「②-2 音名 十二律について」
十二律の起源
②-1でも述べた通り、音名とは絶対的な表現で、定められた音の高さを表すものです。
これらは、元々どのように決まったかというと、「節の無い竹を用意し、三分の一を切るかもしくは付け足して次の音を作る」という方式で作られています。
始めに、「九寸の竹」を用意し、「壱越(いちこつ)※D」。
この竹を三分の一切り、「六寸の竹」で「黄鐘(おうしき)※A」。
三分の一付け足して「八寸の竹」で「平調(ひょうじょう)※E」。
三分の一切って「五寸三三三の竹」で「盤渉(ばんしき)※B」。
三分の一付け足して「七寸一一一の竹」で「下無(しもむ)※F#」
・・・・中略・・・・
となり、一オクターブ上の「壱越」になるまで続けて十二律が作られました。
ただし、「壱越」は「四寸四四二」となり九寸のちょうど半分ではありません。
古来は、この音の違いを聞き分けて、ここから先もこの方法で音を作り続け、六十もの音名が存在したようです。
現代の十二律と声明
現代の一般的な音楽は、「A=440Hz」と定め、そこを基準に一オクターブ上を880Hz、一オクターブ下を220Hzとし、その間の一オクターブを十二等分する「十二平均律」という手法が用いられています。
声明は雅楽を基準に演奏されますので、「A=430Hz」が基準となり、一般的な音楽よりはほんの少し低めで、少し落ち着いた印象があります。
西山声明における「音名」の存在は、「始めの基準音となる宮音」を定める方法としての位置づけであり、その後は「宮商角微羽の五音」をもって、宮音を基準に演奏されます。
これが「耳で唱える」と言われる所以であり、ピアノやキーボードを叩きながら音を取るのとは違い、音の調和を感じながら声を出して演奏する声明の独自性があります。